そういった不満は最初のころは何も問題はないのですが、それが起因して組織活動の低下につながることもあるのです。
大きな問題に発展してから、人事部や本部がようやく気づくということが往々にしてあります。
では、早い段階で気づくことができないのでしょうか。
それを解消する一つの指標が2016年ごろから注目された「モチベーションインデックス」というものです。
これは社員のモチベーションを可視化できるツールとして注目されました。
いかに活用できるのか、この指標の仕組みから考えていきたいと思います。
\1on1面談のやり方が掲載された全13ページの研修資料付/
モチベーションインデックスとは
会社で行われるモチベーションサーベイ(従業員意識調査等)はご存知でしょうか。
これはモチベーションインデックスを知るうえで欠かせないツールです。
モチベーションの向上を支援するにあたり現状把握のための調査分析のために行われた調査であり、従業員へのアンケートやインタビュー等から得られた回答を元に、モチベーション高低の原因を分析するものです。
リンクアンドモチベーションが、2000社以上を対象に、モチベーションについて調査(従業員意識調査)を実施し、そのデータをもとに作った指標がモチベーションインデックスです。
この指標の特筆すべき点は、評価項目の多さにあります。
従業員からみて、「どのようにしてほしいのか」「どうすれば満たされのか」といった観点から、5段階評価で回答するように作られています。
項目としては大きく、「会社にもとめるモチベーションファクター」と「上司・職場に求めるモチベーションファクター」に区分されており、上司や職場、職種別や部署別のスコアが算出されます。
モチベーションサーベイとはどのように行われたのか
では実際に、どのような項目でモチベーションサーベイが行われたのか見ていきましょう。
以下の項目で、会社・上司・職場に対して調査を行います。
この項目を詳細にした質問項目は60項目以上にのぼります。
この回答結果を分析し、モチベーションが高い時に、その次年度の会社の売上がアップしているか調べたところ、相関関係があったとリンクアンドモチベーションが公表しています。
| 会社に求めるファクター | 上司・職場に求めるファクター |
| 会社基盤 | 情報提供 |
| 理念戦略 | 情報収集 |
| 事業内容 | 判断行動 |
| 仕事内容 | 支援行動 |
| 組織風土 | 外部適応 |
| 人的資源 | 内部統合 |
| 施設環境 | 変革活動 |
| 制度待遇 | 継承活動 |
では、一般的な従業員意識調査はどのようなものがあるのでしょうか。
2種類の方法で調査されています。
ES調査(従業員満足度)
ES調査(Employee Satisfaction)とは、従業員が職場環境に満足して仕事をしているか調査するものです。
職場環境とは、報酬や福利厚生といった待遇だけでなく上司や同僚といった人間関係を調査します。
この調査では、従業員からみて、どこに問題点があるのか、どこに不満があるのかを把握していきます。
eNPS調査(従業員ロイヤルティ)
eNPS調査(Employee Net Promoter Score)とは、従業員の所属企業に対する愛着心(エンゲージメント)を数値化したものです。
「自分の職場を親しい人たちに勧められるか」という、従業員のエンゲージメントを調査します。
ES調査は現状の満足度を調べるものであり、eNPS調査の方が、より離職率や生産率との相関性が高いといえます。
リンクアンドモチベーションが実施したモチベーションサーベイは、このeNPS調査が近いのです。
モチベーションインデックスをうまく活用するには
モチベーションインデックスをうまく活用し、数値が上昇している企業の特徴は2つあります。
一つは、モチベーションサーベイを定期的に実施している企業です。
定期的に実施することで、その数値がマネージャーや人事などに共有され当事者意識が生まれます。
その結果、改善活動に積極的に行動するため、数値が改善されるのです。
2年以上サーベイを実施しない企業は数値が改善されないとデータが出ています。
もう一つは、改善活動をすぐに実施し、それについてフィードバックが得られることです。
これは定期的なサーベイ実施にも関係しますが、前回のサーベイから改善活動を実施すると、次のサーベイで数値が反映されます。
このことにより、改善活動が可視化されます。
またそれについての表彰といったポジティブなフィードバックが得れると、現場が自主的に動き出すのです。
現場にモチベーションインデックスは必要なのか
今までは、いかに現場の人材を配置するか、従業員の能力を考えたり、工数をいかに減らすかといった従業員の作業効率をあげる方法を考える組織改革が往々にありました。
そのため、従業員のモチベーションをあげることが、サービスの質の向上や作業効率のアップ、ひいては企業全体の利益につながることは考えられていませんでした。
一部ではそのようなことを考えている経営者や企業はいましたが、明確な科学的な根拠はなかったのです。
そのため、従来は組織の活動に対しての指標がないため、売上目標と違い、明確な目標設定や改善案も立てにくい現状でした。
モチベーションインデックスという指標が出来てからは、企業側も利益につながることを理解し、従業員の満足度を気にする企業が増えてきました。
では、従業員の待遇や不満を解消するためには、どうすればいいのでしょうか。
それは、人事の専門である人事部を強化することだと考えます。
企業の中のたいていの課題は人事制度の見直しをすれば、改善できるのです。
例えば、給与体系の不満があれば、人事評価制度や人事考課の見直しをすればいいでしょう。
また、育成がうまくいかないのであれば、研修制度の見直しを行えばいいのです。
人事部をおいていない企業もあるかと思います。
ですが、10人以上の従業員がいる会社であれば、総務部と切り離して人事部を作ることをお勧めします。
サーベイを行う上での注意事項
サーベイを行っても、従業員から正確な情報を引き出さないと意味がありません。
そのためにどのような工夫がいるのでしょうか。
サーベイの回答内容による不利益がない事を説明する
調査の回答は、上司に知られたりしないこと、個人を特定されないことを説明する必要があります。
従業員の率直な意見を引き出そうとしても、自身の出世に影響が出てしまうのであれば、本音を聞くことができません。
それではサーベイの意味がないのです。
そのことを考慮して回答フォームを作ったり、仕事として業務時間に作業をしてもらう、または回答しやすい場づくりを心がけましょう。
サーベイの結果がどのように活用されるのかを共有する
この調査を行いどう活用されるのか、従業員や職場環境にどう役立つのかといった目的の共有をしてください。
回答者にとってメリットがなければ、積極的な回答を得ることは難しいです。
サーベイの時期を検討する
サーベイを定期的にすることを先ほどお勧めしましたが、上半期下半期の終わり等の忙しい時期はさけるなど、時間に余裕をもって回答できるように配慮しましょう。
回答が負担になるようなことは避けるべきです。
忙しいあまり適当に回答されては、サーベイの結果に影響します。
まとめ
この指標では、従業員のモチベーションが企業の利益と相関していることが証明されています。
今までの企業は、「モノ」や「カネ」といったハード面を考えてきましたが、これから企業が生き残るためには「ヒト」に着目したソフト面を考えていくことが大切ではないでしょうか。
この指標を使いこなすために、定期的にモチベーションサーベイを実施し、従業員「ヒト」を中心とした組織改革を行うべきです。
そのためには、「ヒト」を扱う人事部が企業にとって重要になってきます。
今一度、人事部の強化と人事制度を見直して、従業員のモチベーションの改善に取り組むことをお勧めします。

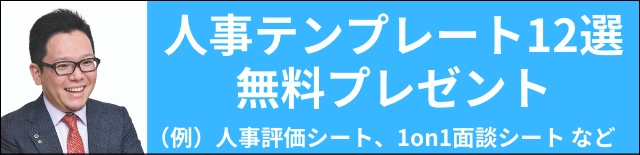
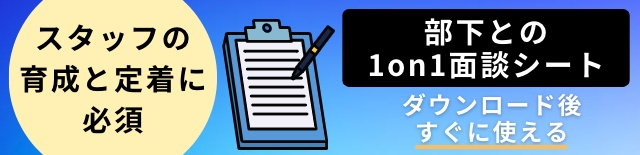
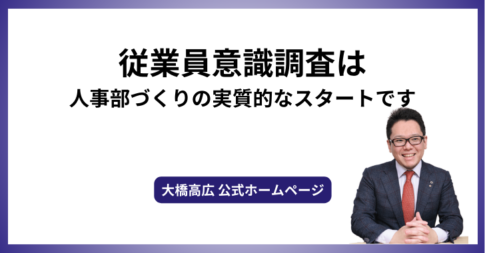
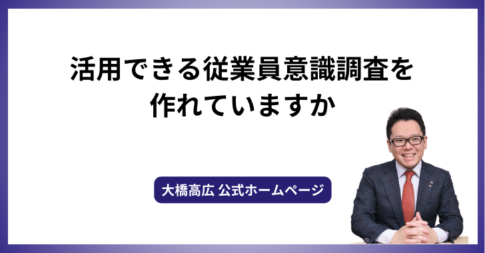

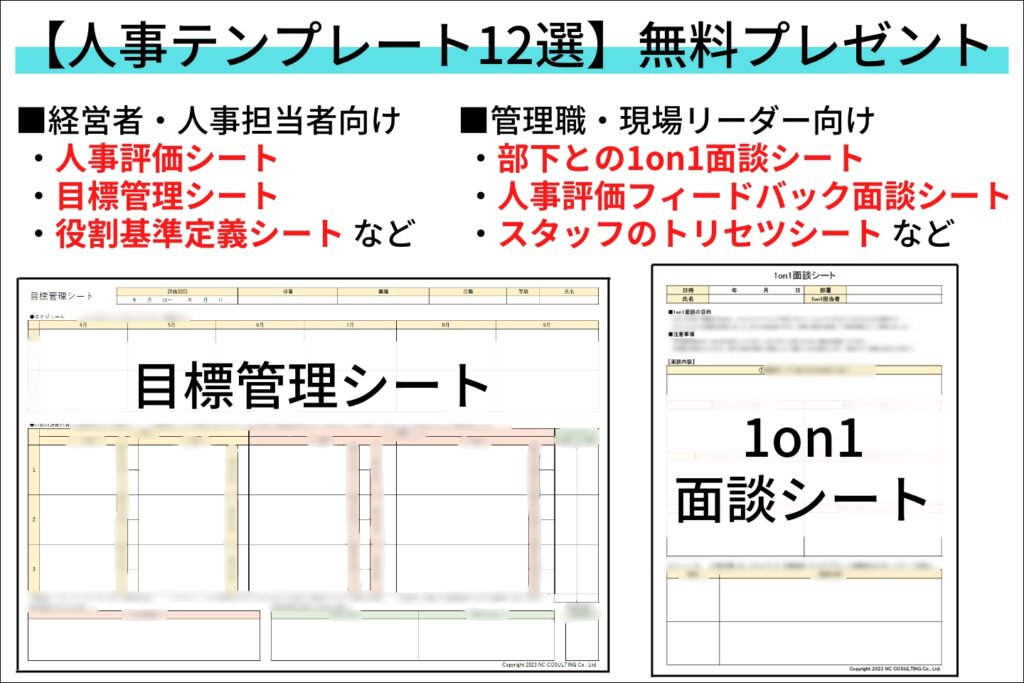
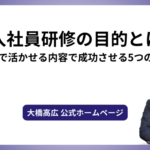
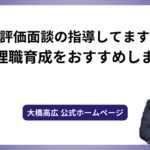
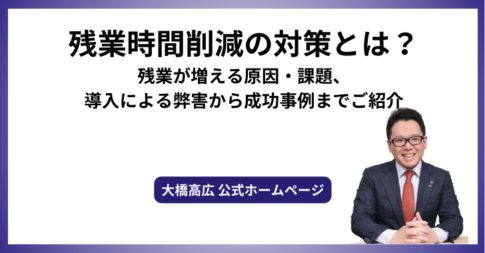
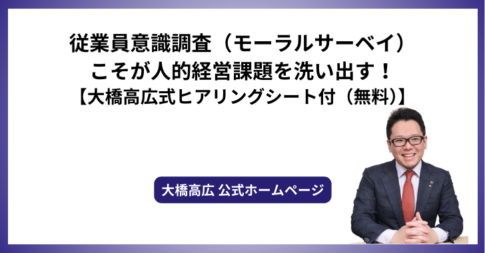
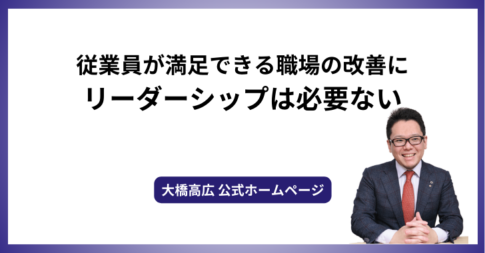
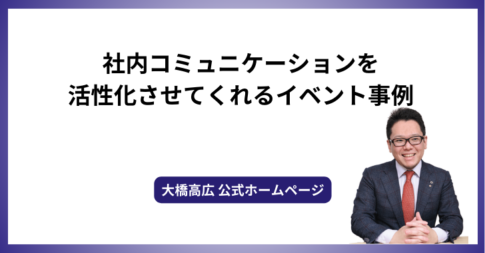
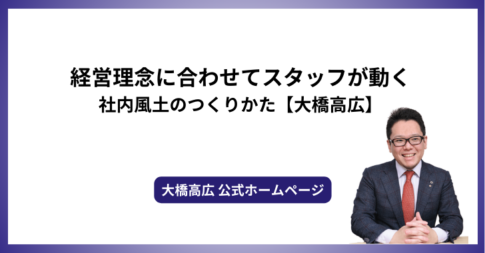
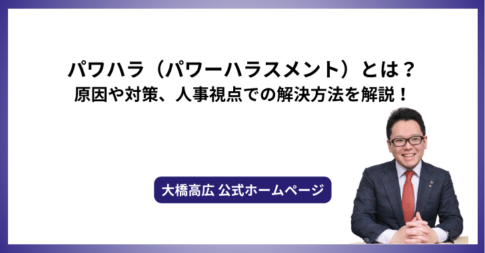
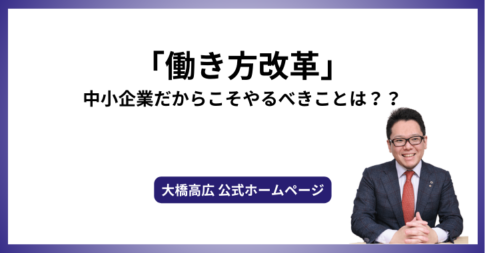
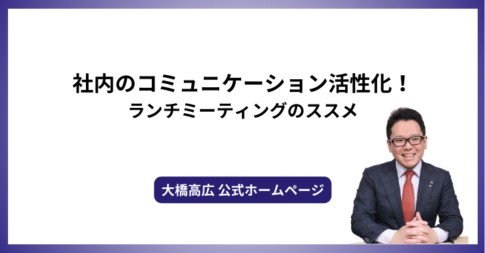
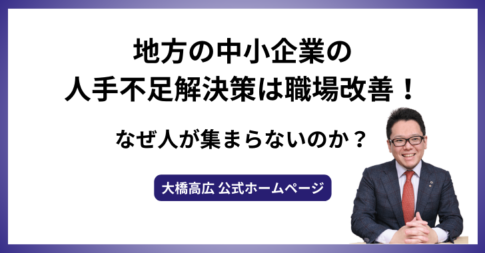


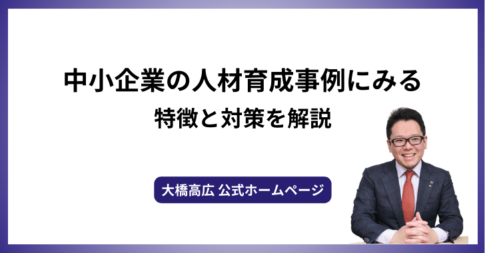


組織・従業員の不満やモチベーションはなかなか可視化できません。