しかし、成果主義と人材定着は「同時に」実現できるのでしょうか?
成果主義は、年齢に関係なく、成果に対して報酬を支払う人事制度です。
この成果主義は人材流動が高い職場環境で成り立ちます。一方で、人材の定着は年功序列などの人事制度と相性が良いと言われています。
今回は、中小企業の経営者が見落としがちな成果主義と人材定着は「同時に」実現できるか?ということについて、解説します。
目指すべき企業成長と人事制度のミスマッチを防ぐ
最適な採用や人事評価制度は何か?
「人事制度の設計・運用」と「マネジメント研修」の専門家。株式会社NCコンサルティング(大阪府大阪市中央区南船場) 代表取締役社長。関西経済同友会 若手の会 幹事。
成果主義と人材定着は真逆です

そもそも、成果主義と人材定着を「同時に」実現することは難しいです。
「成果主義を導入し、優秀な人材だけが残るのようにする」
こういった考えを持つ中小経営者は少なくありません。
もちろん、「成果が芳しくない社員は早々に辞めていただいて結構」というドライな考え方を持つ経営者であれば、成果主義は機能します。
しかし、昨今の人手不足を受けて、優秀な人材を確保したいがために成果主義と人材定着を同時に導入した場合、うまくいきません。
成果主義は人材流動が前提、人材定着は年功序列・定性評価制度と相性が良い
そのため、成果主義を前提に優秀な人材の定着をするためには、人材の流動を促す人事制度や採用活動(成果主義を求める人材)を実施しなければなりません。
目指すべき企業成長と人事制度のミスマッチを防ぐ
最適な採用や人事評価制度は何か?
年功序列を希望する新卒社員が増えている

先日、新入社員へのアンケートで初めて成果主義より年功序列を求める割合が上回りました。
年功序列を希望するということは、成果主義ではなく、そつなく業務をこなし、末長く同じ会社にいたいということです。
人材定着という点では、年功序列・終身雇用制度が最適ということは誰でもわかることです。
しかし、その一方で、野心があり、成果に応じて出世をしたい、つまりは会社の売上や発展に寄与してくれる人材が流出していくことを覚悟しなくてはいけません。
【参考】新入社員は成果主義より年功序列に回帰? 調査開始から36年で初めて逆転 「意識の保守化」と見なす前に企業が取り組むべきことは
なぜ年功序列や終身雇用制度は優秀な人材の流出につながるか、答えは簡単です。言われたことしかやらない社員の分まで、仕事ができる優秀な人材に負荷が寄っていくからです。
年功序列や終身雇用は将来有望な人材に不公平感を植え付けます。
特に資本が小さい中小企業において、年功序列や終身雇用を維持しにくくなっており、成果主義を導入せざるを得ない状況になっています。
しかし、元々の企業文化であった年功序列がなくなったにも関わらず、いまだに人材定着にこだわっている経営者が少なくありません。
目指すべき企業成長と人事制度のミスマッチを防ぐ
最適な採用や人事評価制度は何か?
人材定着をしたいのに的外れなKPIを設定している

人材定着を目指しているのに、成果主義やKPIマネジメント、コンピテンシー評価を導入している経営者がいらっしゃいます。
こうした人材評価は、むしろ人は辞めていきます。
世の中には、高い利益率を誇り、社員の平均年収が高い成果主義の企業が存在します。
そうした企業出身の方が広める、いわゆる「メソッド」なども多く広まっています。
もちろん、そうした企業のメソッドは企業経営において、大いに参考になります。
しかし、成果主義に成功している企業は、そもそも成果主義に適応できる人材が、採用の段階から揃っており、機能しています。
そもそも成果主義ではない、むしろ年功序列や終身雇用を半ば求めていた社員には、成果主義メソッドは当てはまりません。
今の社員に対して、成果主義を導入するのではなく、今いる社員は全て辞めてもらっていいという覚悟で、採用からやり直すべきです。
目指すべき企業成長と人事制度のミスマッチを防ぐ
最適な採用や人事評価制度は何か?
ホワイト化は優秀な人材に負荷をかける

現在、ホワイト企業を打ち出すことで、新卒社員をはじめ、優秀な人材を集めようとする企業が増えています。
しかし、経営者として間違っていけないことは、多様な働き方をはじめ、ホワイト化の基準を「できない社員」に合わせてはいけないことです。
もちろん、育児や介護を必要としている社員に対して、テレワークや時短勤務といった制度は必要です。
そうした社員には、給与で差をつけることで一般社員の不満を和らげる取り組みをしている企業は多いですが、「できる社員」と「できない社員」を明確に分けて評価している企業は少ないと言えます。
ここの評価制度が曖昧だからこそ、優秀な人材が辞めていき、「できない社員」が残っていくという経営者の思惑に反した形で人材が定着していきます(「会社に利益をもたらさない人」が定着する)。
できない社員に合わせた制度は、成果を出せる優秀な人材から(ある意味)搾取する構造を生み出してしまいます。
その結果、優秀な社員から退職していきます。
目指すべき企業成長と人事制度のミスマッチを防ぐ
最適な採用や人事評価制度は何か?
人事施策と目的は合っていますか?

経営者が望む人材採用、人材定着に対して、正しい人事施策をおこなっていますか?
まず経営者として、経営課題の解決策として成果主義が妥当なのか、人材定着が妥当なのかを見極めなければなりません。
先述した通り、成果主義はそもそも人材定着とは逆の施策となります。
- 会社の売上を高めたい:成果主義を前提とした人材流動が大きい職場環境を目指し、そうした環境を求める人材を採用する(採用をし続ける)
- 人材定着を図りたい:年功序列制度に近い人事制度を導入し、必要最低限の業務をこなし、会社の規模を維持する経営にシフトチェンジする
「成果主義の職場だから、福利制度は必要ない」は間違いです。
成果主義でも福利厚生や職場環境の整備は必要です。
福利厚生は人材定着にも効果がある施策ですが、それはあくまで成果主義で頑張る人に恩恵があるような設計が求められます。
福利厚生や居心地の良いだけの職場環境の整備は、優秀な人材を繋ぎ止めることはできないと考えましょう。
目指すべき企業成長と人事制度のミスマッチを防ぐ
最適な採用や人事評価制度は何か?

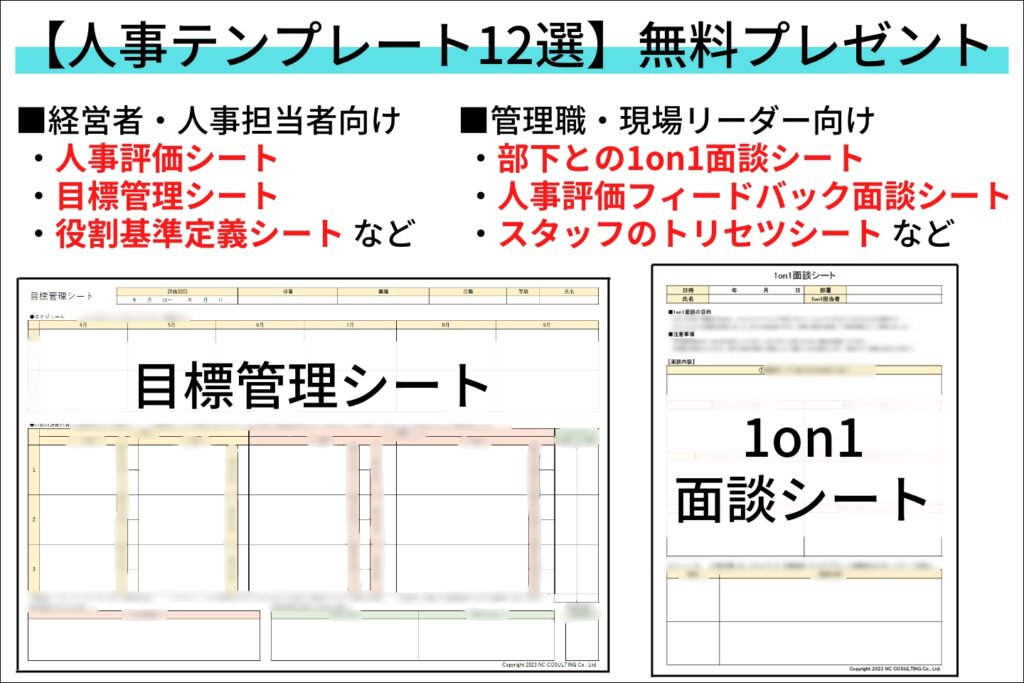
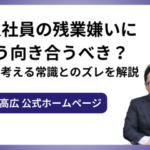

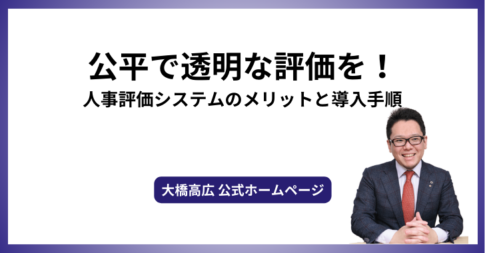
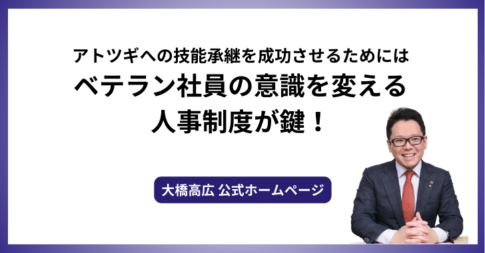
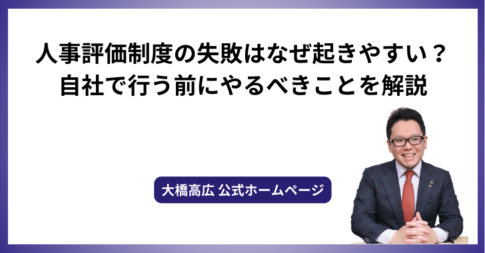
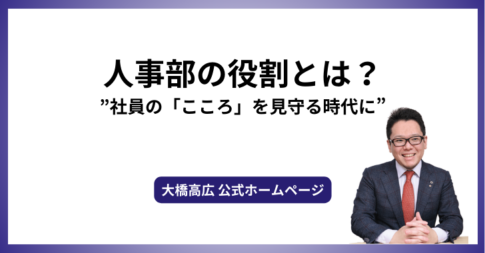
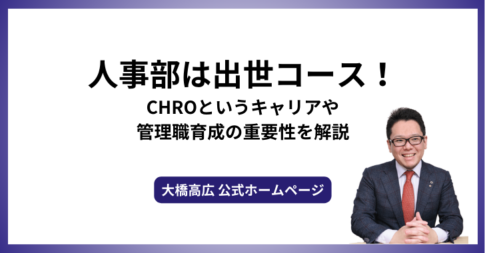
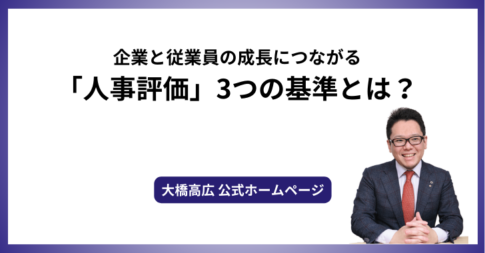
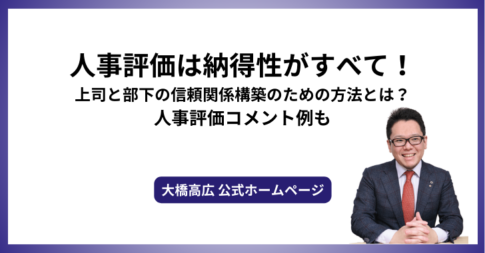
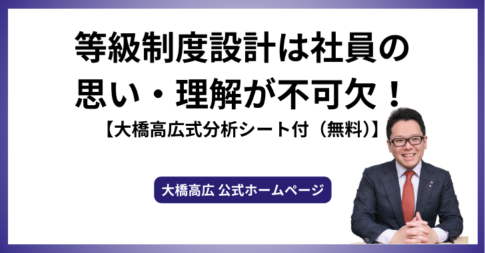
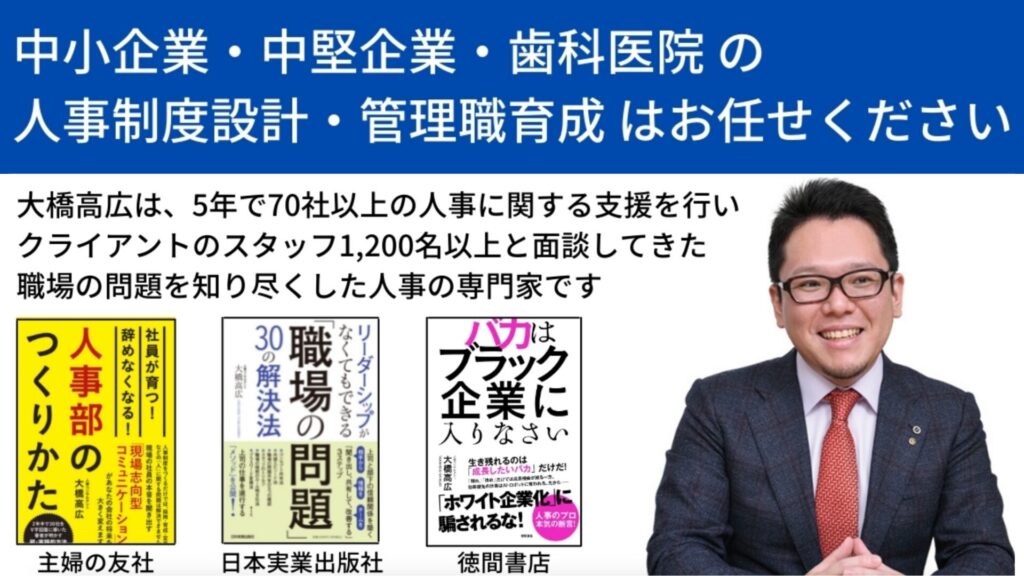


不確実性の高い経営環境において、成果主義を導入し、人手不足から社員の定着を重視する経営者が増えています。