近年、人事管理ツール(SaaS)の発展に伴い、人事評価制度を自社で作成する中小企業が増えていますが、よくこんな質問をいただきます。
「社員のモチベーションが上がらない…」
「人事評価がマンネリ化している…」
「自社に合った人事評価制度を構築したいけれど、何から始めたらいいのかわからない」
「既存の制度を見直したいが、うまくいくか不安だ」
こういったご相談をよくいただきます。
適切な人事評価制度は、社員の成長を促進し、企業の業績向上に大きく貢献します。
しかし、人事評価制度を自社で作成するには、多くの課題が伴います。
本記事では、「人事評価制度、自社で作成できる?」という疑問に答えつつ、人事評価制度作成における課題や"成果を出せる社員"を生み出す人事評価制度について、解説します。
大橋高広(人事コンサルタント)
株式会社NCコンサルティング 代表取締役社長
関西経済同友会 若手の会 幹事
【書籍】
社員が育つ!辞めなくなる!人事部のつくりかた│大橋高広(株式会社主婦の友社)
リーダーシップがなくてもできる「職場の問題」30の解決方法┃大橋高広(日本実業出版)
バカはブラック企業に入りなさい┃大橋高広(徳間書店)
"成果を出す社員"を生み出す
中小企業の人事評価制度設計は
人事評価制度が簡単に作れる時代に…その弊害とは?

人事評価制度は、企業の事業や社風に沿って、自由に作成できる反面、社員が納得できない人事評価になっていると、逆効果になってしまいます。
人事評価制度は、社風や事業の特性に応じた人事評価を自由に設定でき、社員のやる気や給与査定の指標として活用できる優れた制度です。
また、労務と異なり、法令による制限やルールも存在しません。
そのため、中小企業も含めて、各企業が自由に作成でき、運用できます。
近年では、目標管理や人事評価制度を作成できるITツール(SaaS)も増えており、導入も簡単なため、導入だけで満足してしまい、うまく運用ができない企業が増えています。
しかし、人事評価制度の設計や運用の"自由度"があるため、思わぬ弊害を生み出し、最悪の場合、優秀な社員から退職していき、必要とする人材の定着が下がってしまいます。
「自由度が高い」がために、人事評価を受ける現場の社員が不在のまま、作成される人事評価制度
自社で人事評価制度を作成する時の中心的な役割を担うのが、総務部や管理部です。
しかし、この配置こそが機能しない人事評価制度を生み出す原因でもあります。
"成果を出す社員"を生み出す
中小企業の人事評価制度設計は
人事評価制度は、なぜ失敗するのか?

総務部や士業が中心となる人事評価制度の設計がなぜ失敗しやすいのか?
それは、「現場の社員の気持ちがわからないから」に尽きます。
また、士業など国家資格を有する担当者が人事評価制度を担当することも増えています。
しかし、国家資格は素晴らしい資格であり、優秀な人材では変わりありませんが、あくまで保有資格のプロフェッショナル(法律や労務など)であり、"人事のプロ"ではありません。
社会保険労務士や行政書士といった国家資格を保有する方が人事領域のコンサルティングを手掛ける機会が増えています。
誤解を恐れずに言いますが、多くの方が形式的なフォーマットや理論のみを展開される方が多いと言えます。
職場環境の改善は、経営者や管理職に代わって、直接、従業員の声を拾い、職場の問題を可視化させる能力が必要不可欠です。
そうした、現場とのコミュニケーションを徹底して人事改革を手掛ける、士業の方はほぼいらっしゃらないと考えています。
つまり、現場の社員とのコミュニケーションに多大なる時間を使い、現場の社員の気持ちがわかる担当者でないと、現場が納得する人事評価制度は作れません。
人事評価制度を作るためには、現場の社員とのコミュニケーションを重視する人事評価制度の設計専門の人事コンサルタントに依頼する、もしくは人事評価制度の設計責任者に現場の社員を任命する必要があります。
最近では、人事評価制度の作成を自社で行う企業が増えています。その要因は以下が考えられます。
人事評価制度を自社で作成する企業が増えている背景
自社で人事評価制度を作成しようとする企業が増えている背景には、3つのポイントがあります。
- 中小企業にとって、人事コンサルの費用は高額に感じられるケースが多い。
- 業績が安定しない、または物価高・人件費増加の中で、固定費削減の一環として「内製化」志向が強まっている。
- アウトソーシングで作った制度が現場にフィットせず、うまく運用されない経験を持つ企業が増えている。
- 「現場の実情に合った制度は、現場を知る自分たちにしか作れない」という認識が浸透しつつある。
- 「等級」「目標管理」「フィードバック」などの基本概念が普及し、一定の知識をもつ経営者や人事担当者が増えた。
- 書籍やセミナー、YouTubeなどで情報収集がしやすくなり、自力で設計するためのハードルが下がっている。
- 特に若手社員を中心に「透明性」や「公平性」が求められる中、型にはまった制度よりも、自社文化やメンバーに合った制度作りが重要視されている。
- 「社員を巻き込んで一緒に作る」ことで制度への納得感や定着率が高まりやすい。
- 他社の真似ではなく、「自社らしさ」や「経営理念に沿った人材育成」を重視する傾向が強くなっている。
このような背景により、中小企業でも「手間をかけてでも自分たちで設計する」という選択が増えていると考えられます。
しかし、経営者や人事担当者に念頭に置いておいてほしいことは、人事コンサルタントや人事関連ツール、アウトソーシングは”魔法使いではないこと”です。
人事評価制度は、現場力のある人事コンサルタントにアウトソーシングすることが最も効果的ですが、自社の管理職育成や人事評価の運用を適切に行える環境でなければ、どれだけ優れた人事評価であっても機能しません。
"成果を出す社員"を生み出す
中小企業の人事評価制度設計は
人事評価制度が失敗した時のリスクについて

人事評価制度が失敗すると、コストだけでなく、職場環境にも深刻な影響を与えます。
人手不足が深刻な中小企業において、人事評価制度の失敗は必ず避けたい事態です。
特に経営を取り巻く環境が不確実性の高い状況になっている一方で、事業を大きく成長できる機会も増えています。
そのため、何としても人事評価制度の失敗を避けるためにも以下のリスクを把握しておきましょう。
社員のモチベーション低下
不公平感や納得感のない評価制度は、社員のやる気を大きく損ないます。
たとえば、頑張っても評価されない、成果を出していない人と同じ評価を受けているなどの状態が続くと、「やっても無駄」という無力感が広がり、積極性や創意工夫が失われます。
無力感の蔓延は、若手だけでなく中堅社員にも波及する深刻な問題です。
優秀な人材の流出

実力がある社員ほど自身の努力が正当に評価されない状況に敏感です。
報酬やキャリアパスが不透明なままでは、評価に納得できる環境を求めて他社へ移ることが現実的な選択肢になります。
結果として、企業の中核を担う人材が次々に流出し、後任育成や組織の継続力に大きなダメージを与えます。
職場の不信感が高まる
評価に対する透明性が欠けていると、社員同士で「なぜあの人が高評価なのか」といった疑念や不満が広がります。
職場の不信感が高まると、チームワークや協力関係が壊れ、結果として職場の雰囲気が悪化します。
また、上司と部下の信頼関係にも亀裂が入り、マネジメントが機能しづらくなります。
業績が悪化する
評価制度は、社員の行動を企業の方向性と一致させる重要な仕組みです。
その制度が適切に機能しなければ、社員がどのような成果を出せばよいのかが曖昧になり、努力の方向性がバラバラになります。
その結果、組織全体としての目標達成力が弱まり、売上や業績の低下を招く可能性があります。
法的トラブルの可能性も…
特定の社員に対して不公正な評価を繰り返した場合、「差別的扱い」や「不当な配置転換」「昇進差別」などの労務問題に発展するリスクがあります。
最悪の場合、パワハラやメンタル不調による労災申請、訴訟へと発展することもあり、企業の信用失墜や金銭的損失にもつながりかねません。
"成果を出す社員"を生み出す
中小企業の人事評価制度設計は
人事評価制度は社員が納得できるかが鍵

人事評価制度は、社員が納得できる制度になっていて、はじめて機能します。
人事評価制度は、単なる給与決定のツールではありません。
社員のモチベーションを高め、成長を促し、ひいては企業全体の業績向上につながる重要な制度です。
効果的な人事評価制度は、社員の潜在能力を引き出し、組織全体の活性化に貢献させなければいけません。
多くの中小企業が以下の点を重視しないまま、人事評価制度を作成していることがほとんどです。
会社・上司・部下との間で合意、信頼関係が構築できているか
明確で具体的な目標設定は、社員のやる気を最大化するための第一歩です。
曖昧な目標では、社員は努力の方向性を定められず、モチベーションの低下に繋がります。
効果的な目標設定には、以下のポイントが重要です。
| ポイント | 具体的な方法 |
|---|---|
| 会社目標との整合性 | 社員の目標が、部署目標、そして会社全体の目標と整合しているかを確認する → 会社全体の成功にどのように貢献するのかを明確にすることで、社員の責任感とやる気を高められる |
| 上司と部下との間ので合意形成 | 上司と部下がどういった行動と成果を出すことで、人事評価に反映するか、合意が取れていなければならない |
| 目標達成のための支援体制 | 「最近、どう?」と聞く1on1ミーティングを実施する管理職は失格です。 社員の目標達成のために、社員の能力や意欲を最大限に引き出す具体的な支援を約束しているか、管理職のスキルにかかっています。 |
人事評価制度を機能させるには、上司と部下との信頼関係が大切となります。人事評価制度の評価軸に応じて、定量・定性の両方で「ここまで達成できたら評価する」という同意を取りましょう。同時に「できなかった場合、評価しない」と同意を取ることも大切です。
納得感のある評価を実現する管理職の存在
評価基準が曖昧だと、評価結果に納得できない社員が必ず現れます。
この原因は明確で、評価者である管理職の人事評価スキル不足に起因します。
人事評価制度は、管理職が部下を評価するための指標であり、管理職の評価能力を補完する内容でなければなりません。
それは、目標設定や評価の基準を、人事評価制度に照らし合わせて、事前に上司と部下の間で合意形成を取っておくことが大切です。
公平で透明性の高い評価制度を構築するためには、管理職や現場の社員の意見を吸い上げ、評価基準を明確に定義することが大切です。
また、人事評価制度の雛形が作成された時点で、経営者、管理職、見本となる優秀な社員に意見を求め、理解を得る必要があります。
定期的な見直しを行い、常に最新の状況を反映させることも大切です。
1on1ミーティングの有効活用:部下の成長を促進するコミュニケーション

「最近、どう?」と切り出す管理職は、マネジメントスキルがないに等しいと言えます。
評価結果を伝えるだけでなく、具体的なフィードバックをおこなわなければ、社員の成長を促進できません。
効果的なフィードバックの機会こそ1on1ミーティングですが、正しい運用方法を心得ている管理職は多くありません。
| 効果的な1on1ミーティング | フィードバックの方法 |
|---|---|
| 具体的な行動に基づいたフィードバック | 抽象的な表現ではなく、具体的な行動や成果を例に挙げてフィードバックを行う |
| 肯定的な側面と改善点をバランス良く伝える | 良い点と改善点を両方伝え、モチベーションを維持しながら成長を促す |
| 双方向のコミュニケーション | 一方的に伝えるのではなく、社員の意見や考えを聞き、共に解決策を探る |
| 定期的な1on1ミーティングの実施 | 評価時期だけでなく、定期的に1on1ミーティングをおこない、社員の成長を継続的にサポートする |
「最近、どう?」という言葉から始める管理職は失格
1on1ミーティングが機能しているかどうかは、部下である社員にヒアリングをおこなうことが有効です。
「最近、どう?」という言葉を使う管理職は、部下の行動を見てもいなければ、記録もしていません。
早急に管理職研修を実施し、正しい評価能力を身につけさせなければなりません。
1on1ミーティングは、社員の成長を促すだけでなく、上司と部下の信頼関係を構築する上でも重要な役割を果たします。
継続的かつ定期的に1on1ミーティングを開催することで、社員のやる気を高め、企業全体の成長につなげなければなりません。
人事評価制度は、社員の成長と企業の成功を両立させるための重要な制度であると同時に、管理職の育成にも活用できます。
"成果を出す社員"を生み出す
中小企業の人事評価制度設計は
失敗しやすい人事評価制度の特徴

人事評価制度を機能させるためには、「現場の社員が中心」、「管理職が活用できる評価軸」、「運用しやすさ」の3つの点が大切です。
人事評価制度は、適切に設計・運用されなければ、かえって組織に悪影響を及ぼす可能性があります。
自社で人事評価制度を作成する際には、以下の3つの落とし穴に注意しましょう。
現場の社員が不在の人事評価制度
多くの企業が人事評価制度導入に失敗する原因のひとつに、現場の社員が不在のまま、設計されることです。
総務部や士業が中心になって作っても、現場の実情や現場社員にしかわからない気持ちを理解できないまま、人事評価制度を作っても誰も実行しません。
現場の社員が不在のまま、人事評価制度を作っても、制度が形式的に実施されるだけで、形骸化するだけで意味がありません。
管理職やチームメンバーが単なる書類作成作業となり、評価結果が人事考課や昇進・昇給に反映されない、結果的に、人事評価のプロセスが不透明のため、社員は制度への不信感を抱き、やる気を失ってしまいます。
管理職が活用できない評価軸

人事評価制度の公平性を欠くことは、社員のやる気の低下や離職につながります。
これは、人事評価制度に記載されている評価基準を、管理職が活用できていないことに起因します。
管理職が活用できない評価軸は、評価者自身のバイアスや主観的な判断が入り込みやすい原因となります。
管理職が活用できる人事評価制度とは、上司と部下が人事評価において、同意形成を取るにあたり、どの評価基準を中心にするか、相談しながら決定できる評価軸が設けられなければなりません。
まさに、この評価軸こそが"現場の社員"にしかわからない納得感のいる評価軸となります。
現場の社員が人事評価制度の設計に関与できない場合、徹底的にヒアリングを実施するか、現場社員との面談が可能な人事評価制度の設計ができる人事コンサルタントに依頼しましょう。
管理職に負担を強いる人事評価制度
複雑で煩雑な人事評価制度は、ただでさえ忙しい管理職の負担を増やし、優秀な管理職ほど退職していきます。
人材育成のスキルがない管理職の比率が多くなれば、評価の質が低下し、部下の納得がいかない評価結果のフィードバックになってしまいます。
管理職だけでなく、優秀な人材ほど退職していくという負の連鎖につながります。
人事評価制度は、評価者である管理職が活用しやすい制度であってこそ、運用できます。
管理職にヒアリングを重ね、シンプルで効率的な仕組みを作らなければなりません。
失敗しやすい人事評価制度の特徴チェックリスト
上記にご紹介した失敗しやすい人事評価制度の特徴は、"ヒト"に焦点を当てた特徴です。
一般的な失敗しやすい人事評価制度の特徴も同時に把握し、今一度、現行の人事評価制度があてはまっていないか、確認してみましょう!
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価基準が曖昧 | ・「頑張っている」「協調性がある」など主観的な表現が多く、評価者によって判断がブレる。 ・社員が「何をすれば評価されるのか」が分からず、モチベーションが上がらない。 |
| 評価と処遇(昇給・昇進)が連動していない | ・評価結果が給与やキャリアに反映されず、「評価する意味がない」と感じさせてしまう。 |
| フィードバックが不十分 | ・評価後に面談や説明がなく、社員が「なぜこの評価なのか」を理解できない。 ・不満が溜まりやすく、離職リスクが高まる。 |
| 運用が属人化している | ・評価者(上司)の裁量に任せきりで、好き嫌いや相性で評価が左右される。 ・公平性が保てず、社内に不信感が広がる。 |
| 実態と乖離した評価項目 | ・現場業務や職種ごとの特性に合わない評価基準を設定している。 例:営業職に「チームワーク」を過度に求める一方、達成目標が不明確、など |
| 目標管理制度(MBO)が形骸化している | ・目標設定があいまいだったり、期初だけで見直しをしないため、途中で形だけになる。 ・評価と関係ない目標を立ててしまう例もある。 |
| 導入目的が不明確 | ・「とりあえず導入した」「他社がやっているから真似した」だけでは、社内に納得感が生まれず、すぐに形骸化する。 |
"成果を出す社員"を生み出す
中小企業の人事評価制度設計は
大橋高広の人事評価制度設計について
大橋高広の人事コンサルティングは、中小企業を対象とした管理職育成や人事評価制度の立案に強みを持ちます。
「人事を蔑ろにする企業は必ず衰退する」
多くの会社の問題は人事にまつわるものが多いといえます。
大橋高広の人事コンサルティングは「人事評価制度の見直し」と「管理職育成」に特化したソリューションを強みとしています。
採用や人事育成・定着に課題をお持ちの中小企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。
"成果を出す社員"を生み出す
中小企業の人事評価制度設計は

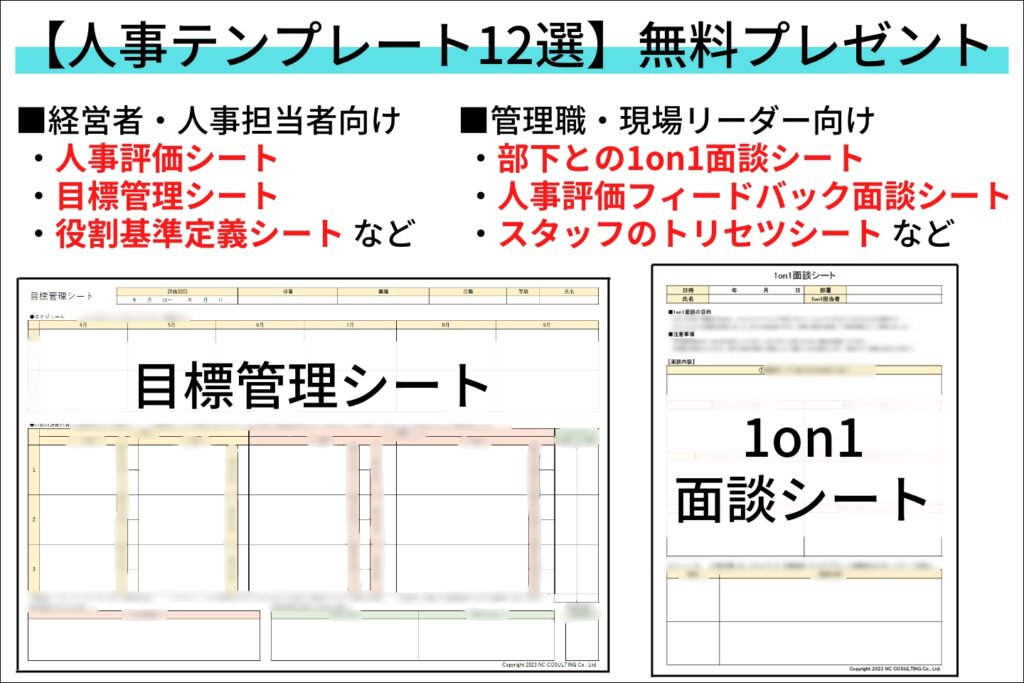
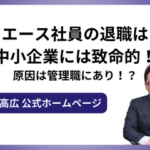
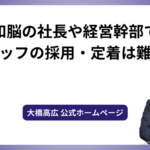

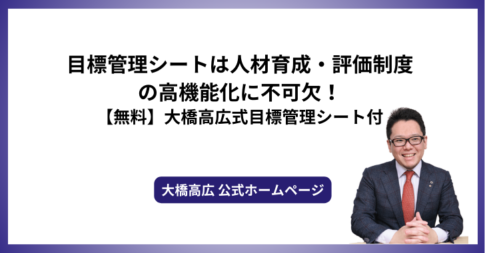
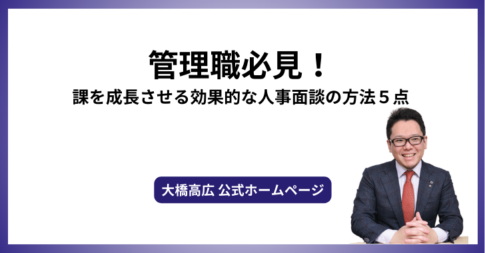
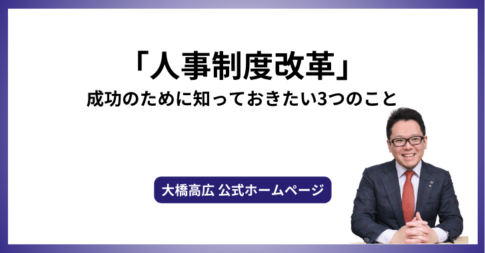
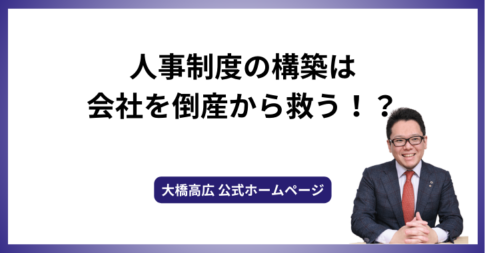
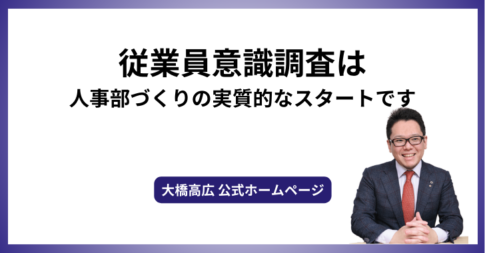
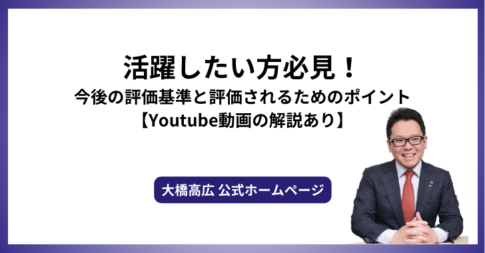
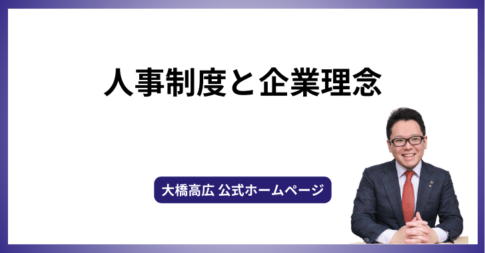
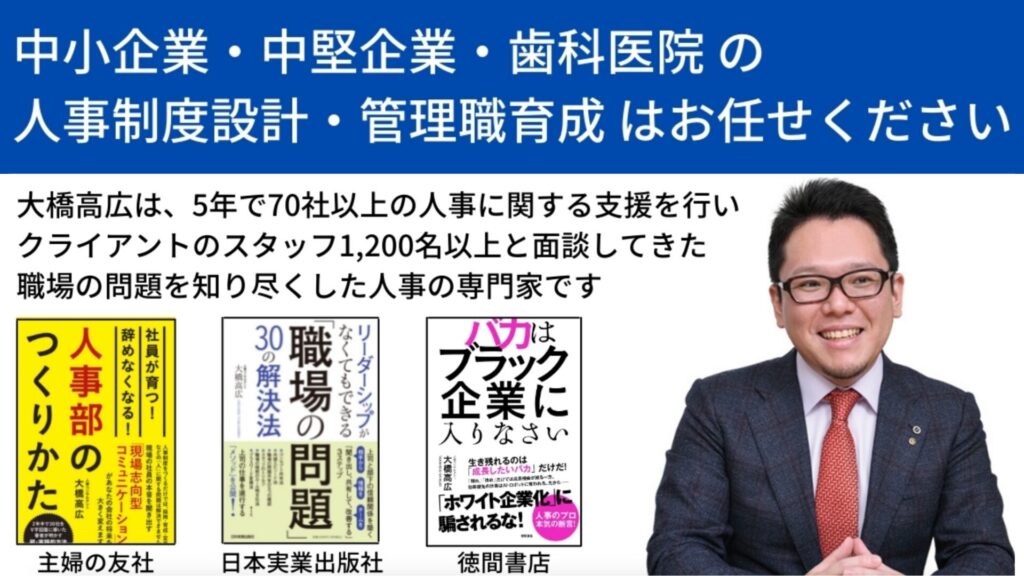


人事評価制度は、企業の事業や社風に沿って、作成できる反面、社員が納得できない人事評価になっていると、逆効果になってしまいます。