最賃1,500円時代が現実味を帯び、偏差値に限らず、大学卒であれば初任給が26〜30万円となることもめずらしくなく、企業の人件費負担は増す一方です。
しかし、問題はそれだけではありません。
労働者の権利保護が強化された一方で、さまざまなハラスメントに気をつけながら、人材マネジメントを担う上司(管理職)の負担も増していきます。
無理に人を集めるだけの昭和的な採用を続ければ、想定よりもパフォーマンスが低い社員や周りに悪影響を与える社員を抱え込むリスクも高まり、職場で真面目に働く優秀な社員ほど疲弊して辞めていくという最悪の事態に陥ります。
会社に残るのは組織を支えるどころか蝕む人材ばかりという最悪のシナリオすら現実のものになりつつあります。
こうした状況に危機感を覚える企業や経営者の中には、AIで業務を代替したり効率化したりする動きが加速しています。
AIは人手不足の一部を補う心強い武器です。しかし、AIに全てを任せて問題が解決するほど、現場は単純ではありません。
会社に本当に必要なコア人材を守りながら持続可能な組織を作るために、「ヒト×AIの最適バランス」という視点から「これからの人事戦略」をご紹介します。
AIで業務を代替すると同時にコア人材の育成が不可欠です
管理職育成を同時に進めることが大切です
「人事制度の設計・運用」と「マネジメント研修」の専門家。株式会社NCコンサルティング(大阪府大阪市中央区南船場) 代表取締役社長。関西経済同友会 若手の会 幹事。
採用難・離職率増加の背景とリスク

人口減少が進む中、若年層と中間管理職を中心に採用難が続いています。
さらに今後、人件費の高騰は避けて通れず、コストをかけるべき人材を見極め、代替が可能な業務は効率化していかなければなりません。
昭和型の「数合わせ採用」はもはや限界
少子高齢化の影響で多くの業界で慢性的な人手不足が続いています。
「求人を出しても応募が来ない」
「来たとしても条件が合わずに辞退される」
こんな悩みを抱える企業はめずらしくありません。
追い込まれた末に「とにかく誰でもいいから人を入れよう」という昭和的な採用を続ける中小企業がいまだに多く残っています。
しかし、こうした採用は問題社員を招きやすい職場を生み出してしまいます。
採用基準が曖昧になれば、仕事への意欲が低く、向上心がない人材が混ざりやすくなります
こうした社員の存在は、直接的な業務停滞だけでなく、本当に守るべき”真面目”で”優秀”なコア社員に余計な負担をかけてしまい、エンゲージメントやモチベーションを大幅に下げてしまいます。
結局、現場を支えていた優秀な人材が耐えられずに辞めていく
——これが「とりあえず、ヒトを雇えばいい」と考える中小企業が陥る負の連鎖です。
「人がいないから誰でもいい」という考え方こそが、企業を内側から弱らせていることに、そろそろ本気で向き合わなければなりません。
最賃上昇・初任給高騰で人件費リスクはさらに増大
こうした採用難に追い打ちをかけるのが、賃金水準の上昇です。
最低賃金が1,500円を突破するのは時間の問題とされ、どの業界でも人件費負担は年々増えています。
2025年時点でも都市部、地方に限らず、新卒初任給が26万円〜30万円程度になることはめずらしくなくなっています。
どの企業も「高い人件費を払って雇った人材が想定よりもパフォーマンスが低い社員だった」というリスクにさらされる可能性が高まっていることを、経営者は強く認識しなければなりません。
高いコストをかけて雇い、さらに現場に負担をかけて、真面目な社員が辞めていく。
こうした職場環境や会社の状況こそ、企業経営の持続性を危うくする根本的な問題といえます。
AIで業務を代替すると同時にコア人材の育成が不可欠です
管理職育成を同時に進めることが大切です
悪影響をもたらす社員を入れない・増やさない仕組みが必須

悪影響をもたらす(問題社員)が職場に紛れ込むのを防ぐためには、採用段階の「見極め」が何より重要です。
履歴書や面接だけでは分からない部分を補うために、適性診断や性格診断、リファレンスチェックを活用する企業が増えています。
しかし、手間をかけても、悪影響をもたらす社員を完全に防ぐことは難しいといえます。
そこで大切なことは、面接で問題のある社員かどうか見極めることができる、優秀な管理職の存在です。
最適な職場環境を実現するためには、採用や現場のマネジメントを担う管理職の育成が欠かせません。
また、入社後の行動を可視化し、問題行動を見逃さない仕組みも欠かせません。
AIやHRテックを活用した行動データを分析し、離職リスクや問題行動を早期に察知することも効果的と言われていますが、人材育成やマネジメントスキルを持つ上司(管理職)がいなければ、機能しません。
AIやHRテックを活用しながら、人間でしか賄うことができない管理職を育成することが大切です。
管理職などコア人材の育成は、真面目な社員や会社に利益をもたらしてくれる社員が安心して働き続けられる職場環境を実現する鍵です。
AIで業務を代替すると同時にコア人材の育成が不可欠です
管理職育成を同時に進めることが大切です
人材不足による業務負荷はAIで代替する

職場に悪影響を与える人材が組織内に残ると、周囲の真面目な社員に余計な負担がのしかかり、職場の雰囲気は徐々に悪化していきます。
こうした負の連鎖を断ち切るために注目されているのが、AIの活用です。
AIは人手不足を補うだけでなく、無責任な働き方をする人材に依存しなくても業務を回せる土台を築く強力な手段になります。
例えば、定型的なルーチンワークやミスが許されない入力作業は、真面目な社員が肩代わりすることで成り立っていることが少なくありません。
しかし、AIを導入すれば、人の手に頼らずに正確かつ迅速に処理できるため、責任を果たさない人材の存在に左右されにくくなります。
また、シフト管理や勤怠集計といった煩雑な作業もAIに任せれば、属人的な業務が減り、業務の透明性が高まります。
こうしたデータが可視化されることで、職場の状態を管理職が把握しやすくなり、不公平な負担が生まれにくくなるのも大きな利点です。
さらに、AIを活用する際はただツールを導入するだけでなく、現場の業務フローに適合させ、誰もが簡単に扱える形に整えることが重要です。
運用を現場任せにすると、逆にAIが形骸化し、負担を増やしてしまうこともあるため、導入後の活用方法や従業員への研修も欠かせません。
AIは人材の代わりではなく、真面目に働く人たちの負担を減らし、組織全体の健全性を守るパートナーです。

職場に悪影響を与える人材に頼らずにすむ業務体制をつくり、限られた人材を価値の高い仕事に集中させることこそが、これからの持続可能な組織づくりの要となるでしょう。
AI活用が注目される理由と落とし穴

中小企業の経営者がAI活用に注目する理由と思わぬ落とし穴も把握しておきましょう。
人材育成とマネジメントができる管理職を中心としたコア人材を守りつつ、AIを導入することが不可欠です。
「AIで業務を代替したい」というニーズが増加
職場に悪影響を与える人材の雇用リスクや即日退職する人材が増えるという、人手不足と人材定着の両面で困り果てた中傷企業は、必然的にAI活用に注目が集まっています。
定型的な事務作業や日報入力、シフト管理といった業務をAIに置き換え、人の負担を減らす取り組みはすでに多くの現場で始まっています。
「AIでできることはAIに任せて、人は付加価値を生む仕事に集中する」
この考え方は間違っていません。
むしろ、ルーチン業務を人が延々と行っている状態こそが、職場に悪影響を与える社員にとって“居座りやすい”環境を生みがちです。
単純作業をAIが代替することで、成果が見えやすい職場に変われば、責任を果たさない人が残りにくくなるメリットもあります。
DX崩れのAI導入で現場が疲弊する失敗例
一方で、AI活用には注意が必要です。
よくあるのが、「DXを推進します!」と意気込んでAIツールを導入したものの、現場の業務フローに合わずに使われなくなるパターンです。
特に中小企業では、AI導入をベンダー任せにした結果、現場に丸投げされ、逆に負担が増えるという事例が少なくありません。
また、専門的な知識を有しない人材がAI活用を信望し、誤った成果物を出力してしまい、何も成果をあげられないという事態も増えています。
特に今まで簡単な業務に終始し、今まで自分のスキル向上に時間と労力をかけてこなかった人材ほどAIを信望しやすく、「自分は優秀な人材」と勘違いしてしまう人材が増えると職場環境は悪化してしまいます。
AIを導入しただけで問題社員が減るわけではなく、AIを活かす仕組みと、それを使いこなす人材がいてこそ、本来の効果が発揮されます。

AIはあくまで“道具”です。人事も現場も使い方を理解しなければ意味がありません。
AIで業務を代替すると同時にコア人材の育成が不可欠です
管理職育成を同時に進めることが大切です
これからの人事戦略に必要なのは「ヒト×AIの適正バランス」

AIはあくまで“道具”です。人事も現場も使い方を理解しなければ意味がありません。
これからの人事戦略は、人材育成やマネジメントができるコア社員(上司:管理職)をしっかりと育成しながら、AIを導入し、業務最適化をおこなっていかなければなりません。
マネジメント層とコア人材を守り抜く重要性
これからの時代、最も大切なのは「会社を根幹で支える人材を守る」ことです。
現場作業を真面目に担う人たちは、経営やマネジメントには関心がない人材も増えています。
だからこそ、彼らを支え、職場全体を俯瞰して回せるマネジメント層の存在が不可欠です。
無理に人数を増やし、問題社員を抱え込めば、コア人材に負担がかかり、結局辞めてしまいます。
大切なことは、限りある人件費を職場に悪影響を与える社員に搾取されるのではなく、マネジメント力のある人材や現場リーダーに集中的に投資することです。
AIリテラシーを持つ人事部門を育てる
同時に、AIを有効に活かすためには人事部門のリテラシー強化も不可欠です。
「AIをどう活用するか」
「AIで何を置き換え、人でしかできないことは何か」
——これを考え、現場に落とし込める知識とスキルが人事に求められます。
AI研修やデジタルツール活用のノウハウを人事部門自身が習得することで、形だけのAI活用で終わらない、組織に根付く人事DXが実現できます。
AIを活かすのは、結局は“ヒト”です。
人とAI、それぞれの強みを最大限に活かすバランス感覚こそが、これからの人材戦略の要になります。
AIで業務を代替すると同時にコア人材の育成が不可欠です
管理職育成を同時に進めることが大切です
まとめ:人材の持続可能性が企業の命綱
人材不足、離職増加、職場に悪影響を与える社員の横行
——こうした問題は、一時的なものではなく、構造的な課題として中小企業に突きつけられています。
だからこそ「誰でもいいから採用する」という古い常識は捨て、限られた人件費を真に価値を生む人材に集中させる発想が不可欠です。
AIは魔法の杖ではありませんが、正しく使えば職場に悪影響を与える社員の影響を最小限に抑え、真面目で優秀な社員が働きやすい環境を守る大きな助けになります。
コア人材を守り抜き、育て、AIで業務効率を高める
この「人×AIの最適バランス」を見極め、組織全体で実践することこそが、これからの企業の持続可能性を支える最大の鍵です。
真面目に働く人が報われる職場を、AIと"ヒト"の力で取り戻しましょう。

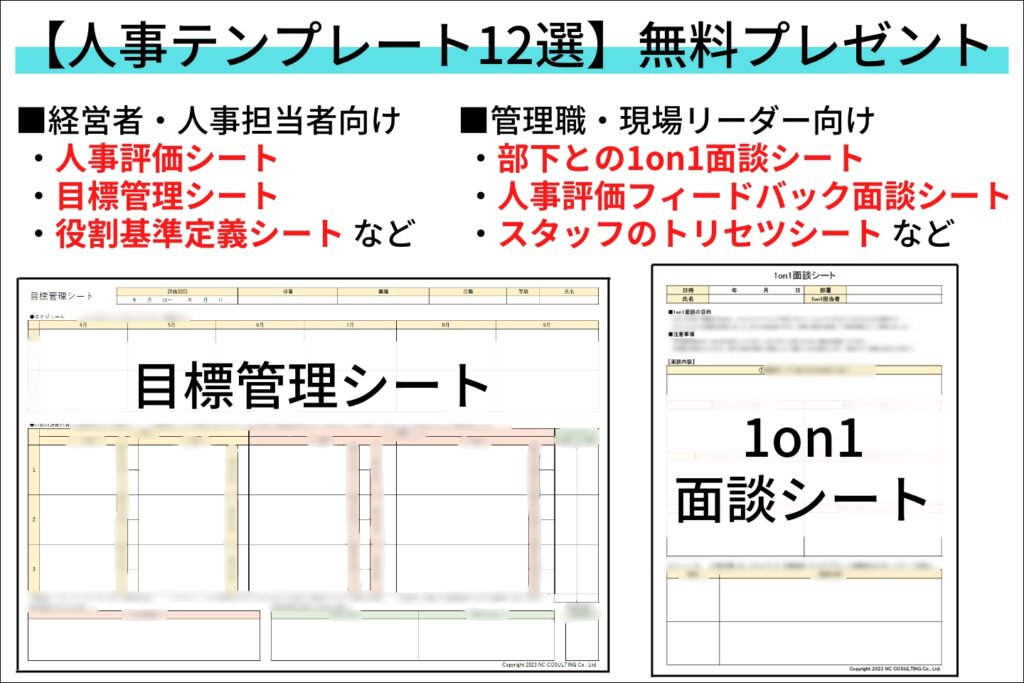

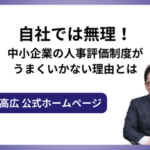
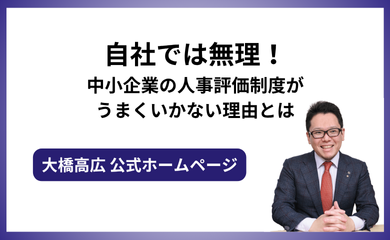
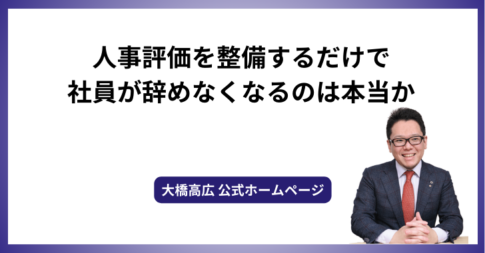
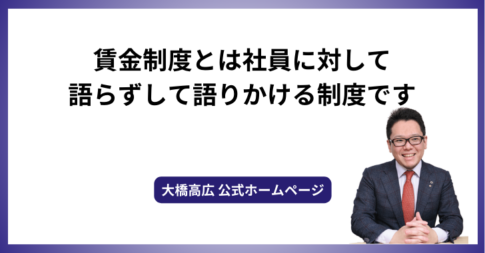
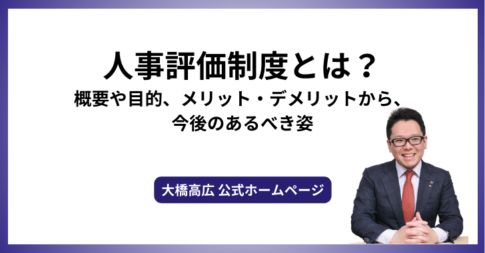
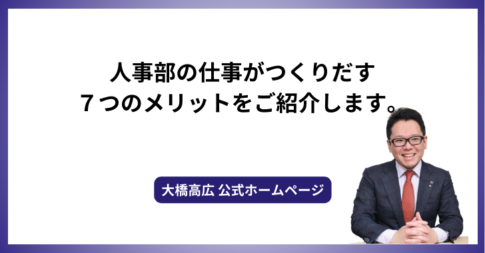
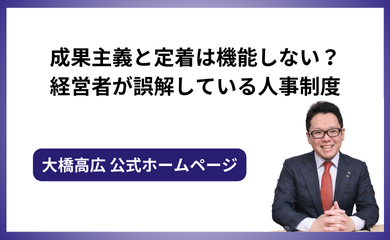
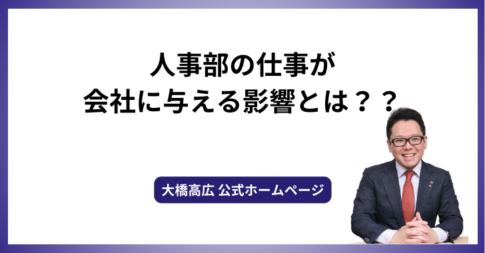
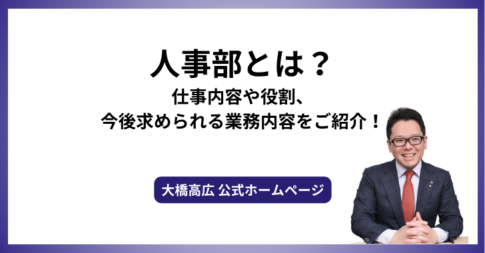
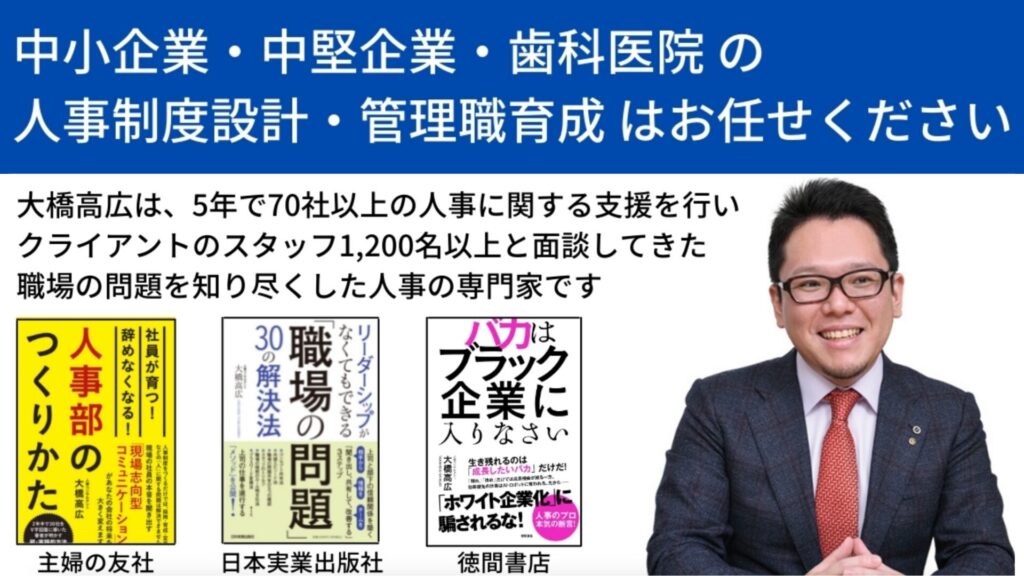


人材不足が深刻化する今、採用と定着のあり方はかつてないほど企業経営を左右するテーマになりました。